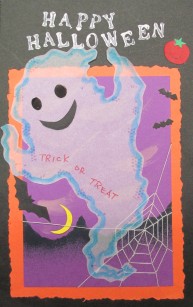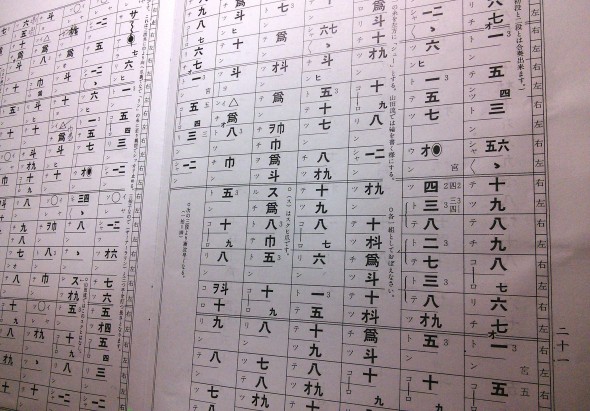一月に日本に来てからHub京都というコミュニティセンターにを見つけました。Hub京都では色々なイベントがあるから、この経験を通して同志社の同級生だけではなくて、京都府から集まる人々にも会える可能性があります。Dojo for Changeをはじめ、Hub Kitchenや Bar Hubなどと言うエベントでコミュニティを手伝う人がよく参加したり、論議したり、お金を拠出したりします。Hubの一般的な目的は人々の間に親しみを浸透させることです。
2月12日にHubのブログのためにDojo for Changeに行って、そういうイベントの内容を要約しました。「美しさに真実があります。でも、混乱の中で美しさがあります。」と語ってくださったのは、「創造性の求心力」と言う特別なDojo for Changeで発表して下さった黒崎輝男でした。この世界でお金が必ず要るけど一番大切なのは自分の夢のだとか。黒崎さんは多くの抽象的な言葉を使ったので最初に分かりにくかったですけれども、えりさんというHubの幹事のおかげで翻訳してくれたから深く理解できてよかったです。
Hubで他の義務はエクセルの中にえりさんがもらった名刺の内容を入ることや、イベントの部屋のレイアウトの図を書くことが含まれています。たいてい忙しいですがこれまでHubを楽しんできました。